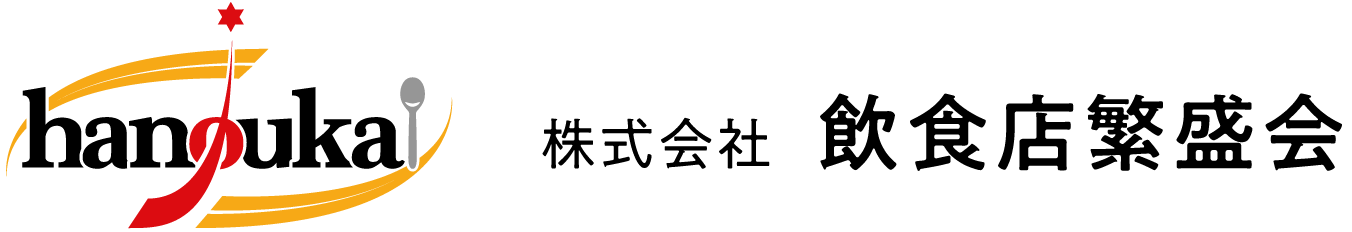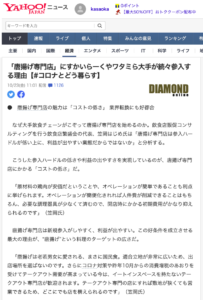ここでいう注文率とは、お客様の来店人数のうち何%のお客様が、その商品を注文したかという割合です。
計算式としては、
注文率 = 注文数 ÷ 来店人数
例えば、うちの台湾のお店は、主力商品が餃子とタンメンなので、最低限、その2つのカテゴリの注文率を週単位で記録しています。
1週間分の餃子カテゴリの注文数が、800注文(皿数)で、1000人の来店が合った場合は、
800注文 ÷ 1000人 = 0.8
となります。
つまり、このお店は、100人来店したら80%の80人が餃子を頼むことになります。
これを週単位で記録していくと、どの商品もある程度一定割合の幅の中に収まるようになります。
例えば、台湾のお店なら0.7〜0.75くらいで安定しています。
100人のうち70人〜75人が餃子を注文するということです。
もっと正確に言い換えると、100人来店したら70皿〜75皿餃子が出るということです。
で、この数字をどう使うかですが、次の3つの指標として使います。
1.その商品をより注文してもらうための目標設定
100人中30人しか餃子を頼んでもらえなかったら、餃子はそのお店の看板商品とは言えません。看板商品として認知してもうために、この数値を0.7以上にしようと言った目標設定をしてスタッフと共有します。
2.仕入れ・仕込みの精度を上げる
例えば、水曜日のランチの平均人数が100人だったとします。であれば、餃子の仕込みは、70〜80人分仕込めばいいといった目安になります。それにより、ロスの軽減、労働時間の適正化などができます。
3.新商品投入時の判断材料、新商品投入後の影響力の考察
新商品を投入するときに、その新商品をどのくらい仕込めばよいかの判断材料にもなり得ます。例えば、餃子カテゴリの1つの商品を新商品に入れ替えるとしたら、最初に投入する仕込み量の目安がわかりますし、新商品によって注文率が変われば影響力がわかります。
商品の注文率は、メニューブックの表現の仕方やレイアウトでも変わってきます。なので、メニューブックリニューアルした後の効果の指標としても使えます。
笠岡@飲食店繁盛会
]]>投稿者プロフィール

- 飲食店コンサルタント/販売促進士
- 飲食とITの専門家。1,000件以上の飲食店コンサルティング実績から再現性のあるノウハウを体系化し、全国の飲食店の売上と利益を上げている。また、中国や台湾、UAE等の飲食店のコンサルティングやプロジェクトを手掛けている。著書に「MSP繁盛プログラム〜どの飲食店でも最短で確実に売り上げを上げる方法」(販売促進士日本フードアドバイザー協会ブックス)、「売れまくるメニューブックの作り方」(日経BP社)、「繁盛飲食店にする1分間セミナー」 (同文館出版)等。「売れまくるメニューブックの作り方」は、台湾と中国でも出版されている。一般社団法人販売促進士日本フードアドバイザー協会代表理事。株式会社 飲食店繁盛会代表取締役。三商餐飲顧問股份有限公司董事。

私たちがあなたのお店にお役に立てることは
ございませんでしょうか?
もし、何かありそうでしたら、
お気軽にお話を聞かせてください。
無料相談の詳細・お申し込みはこちら
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問など
お気軽にお問い合わせください