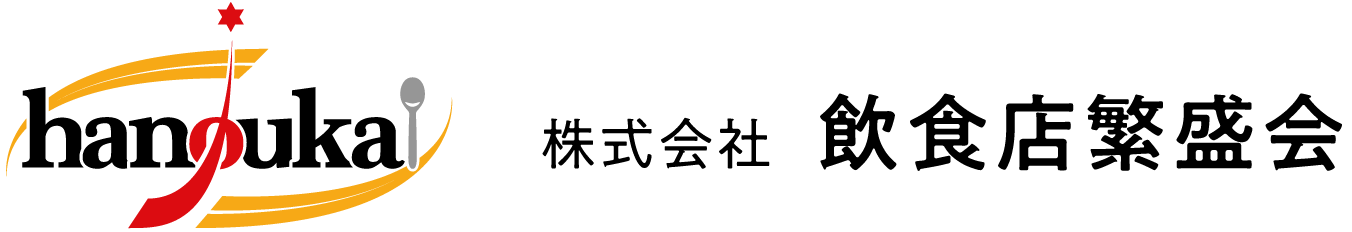# 初めての飲食店開業で絶対やってはいけない5つのこと
# 初めての飲食店開業で絶対やってはいけない5つのこと
飲食店の開業を検討されている方、または開業準備を進めている方にとって、重要な情報をお届けします。飲食業界は参入障壁が低く見えますが、実際には多くの落とし穴が存在します。統計によれば、新規開業した飲食店の約7割が3年以内に閉店するという厳しい現実があります。
この記事では、20年以上にわたり多くの飲食店オーナーをサポートしてきた経験から、「絶対に避けるべき失敗」を厳選してご紹介します。許認可手続きの見落としから不適切な資金計画、コスト管理の誤り、立地選定の失敗、そしてメニュー開発の致命的なミスまで、実例を交えて解説します。
これから飲食店を開業する方はもちろん、すでに経営されている方も、自店の運営を見直す良い機会になるでしょう。成功への近道は失敗を避けることから始まります。この記事で紹介する5つのポイントを押さえることで、開業後の苦労を大幅に減らし、安定した経営基盤を築くためのヒントを得ていただければ幸いです。
飲食店経営の成功を目指す方々にとって、価値ある情報となることを願っています。それでは、飲食店開業で「絶対にやってはいけない」重要ポイントを見ていきましょう。
1. **飲食店開業前に必ず確認すべき許認可手続き - 無知が招く営業停止リスクを回避する方法**
タイトル: 初めての飲食店開業で絶対やってはいけない5つのこと
見出し: 1. 飲食店開業前に必ず確認すべき許認可手続き - 無知が招く営業停止リスクを回避する方法
飲食店開業において、許認可手続きの重要性は何よりも優先されるべき事項です。多くの新規オーナーが陥る最大の失敗が、この手続きの軽視や後回しです。実際、食品衛生法に基づく営業許可を取得せずに営業を開始し、後日行政処分を受ける事例は後を絶ちません。
飲食店開業に必要な主な許認可には、保健所への「食品営業許可申請」、消防署への「防火対象物使用開始届」、そして酒類を提供する場合は税務署への「酒類販売業免許申請」があります。これらは開業の最低30日前までに申請する必要があり、特に食品営業許可は施設基準の検査が厳格です。
具体的な事例として、東京都内で開業したラーメン店が許可なく営業を開始し、3ヶ月後の抜き打ち検査で発覚、営業停止処分と罰金刑を受けた例があります。また、大阪市内のバーでは消防法の基準を満たしていなかったために改装工事を余儀なくされ、追加で数百万円のコストが発生したケースもありました。
対策としては、まず開業予定地の所在する自治体の保健所に相談し、必要な許認可リストを入手することが肝心です。次に、飲食店に精通した行政書士や社会保険労務士などの専門家に相談することで、申請書類の不備や見落としを防げます。日本フードサービス協会や各地の商工会議所も有用な情報源となります。
許認可取得の手続きは最短でも1ヶ月、複雑な案件では3ヶ月以上かかることもあるため、開業スケジュールに余裕を持たせるべきです。また、許認可申請の費用は自治体によって異なりますが、基本的な食品営業許可だけでも数万円から十数万円の費用がかかることを計画に織り込んでおきましょう。
無知や焦りから許認可手続きを軽視することは、せっかくの飲食店開業の夢を台無しにしかねません。正しい知識と計画的な準備こそが、スムーズな開業への近道なのです。
2. **飲食店の資金計画で失敗しないための徹底ガイド - 元銀行員が教える返済可能な借入額の見極め方**
2. 飲食店の資金計画で失敗しないための徹底ガイド - 元銀行員が教える返済可能な借入額の見極め方
飲食店の開業資金計画は成功と失敗を分ける重要な分岐点です。私が銀行融資担当として多くの飲食店オーナーを見てきた経験から言えるのは、返済計画の甘さが廃業の大きな原因になっているという事実です。日本政策金融公庫の調査によると、飲食業の5年生存率はわずか30%程度。その多くが資金繰りの失敗に起因しています。
まず押さえておくべきは、飲食店の開業資金の内訳です。一般的に物件取得費または保証金、内装工事費、厨房設備費、家具・備品費、そして運転資金(最低でも半年分)が必要となります。都心の60坪クラスの居酒屋を例にすると、3,000万円から5,000万円の初期投資が必要となるケースが多いでしょう。
しかし、多くの新規オーナーが陥る罠は「売上予測の楽観視」です。実際の数字をお伝えすると、客単価3,000円の店舗で席数30席、回転率1.5回/日としても、1日の最大売上は約13万5千円。稼働率を考慮すると月商300万円程度が平均的な見込みとなります。この売上から家賃(売上の8〜10%)、原価(30〜35%)、人件費(30%前後)、その他経費(10%)を差し引くと、月の利益は約45万円程度です。
ここから返済額を考えると、月20万円以上の返済は資金繰りを著しく圧迫します。メガバンクや地方銀行では、この返済負担率(月商に対する返済額の割合)が7%を超えると融資審査が厳しくなる傾向があります。つまり、月商300万円なら月の返済額は21万円程度が上限と考えるべきです。
具体的な借入可能額の計算方法は、返済額×返済回数で算出できます。例えば月20万円の返済で5年(60回)返済なら1,200万円が借入上限です。ここで注意すべきは金利の影響です。日本政策金融公庫の新創業融資(金利1.4〜2.3%程度)と民間銀行(3〜5%)では大きく異なります。
さらに、多くの失敗例から学ぶべき教訓として、「複数の金融機関からの借入れによる返済計画の複雑化」があります。メインバンク以外に、信用金庫やノンバンクから借入れを重ねると、返済スケジュールが煩雑になり、資金繰りが悪化するリスクが高まります。
最後に、銀行員視点で伝えたい重要ポイントは、最悪のシナリオを想定した資金計画です。開業後3ヶ月は売上が安定せず、予測の50%程度しか達成できないケースも少なくありません。そのため、少なくとも半年分の運転資金(家賃、人件費、仕入れ等のランニングコスト)を別途確保しておくことが必須です。これが「資金の見極め」の本質です。
みずほ銀行や日本政策金融公庫などが提供する創業計画書のテンプレートを活用し、専門家のチェックを受けることで、より現実的な資金計画を立てることができます。開業前の緻密な計画が、飲食店成功への第一歩となるのです。
3. **開業初年度の赤字を最小限に抑える戦略 - 先輩経営者が語る「やってはいけない」コスト削減の落とし穴**
タイトル: 初めての飲食店開業で絶対やってはいけない5つのこと
見出し: 3. 開業初年度の赤字を最小限に抑える戦略 - 先輩経営者が語る「やってはいけない」コスト削減の落とし穴
飲食店開業の初年度は、多くの経営者が赤字との闘いを経験します。この時期にコスト削減を考えるのは自然なことですが、間違った削減方法は将来的な成長を妨げ、最悪の場合は閉店に繋がることも。成功した飲食店オーナーたちの失敗談から学ぶ、絶対に避けるべきコスト削減の落とし穴を紹介します。
安易な食材原価の削減は長期的な自殺行為
「原価率を下げれば利益が上がる」という単純な計算で、安価な食材に切り替える経営者は少なくありません。しかし、実際にはこれが最も危険な選択の一つです。
銀座で10年以上人気を維持する寿司店「鮨 かねさか」の金坂氏は「開業当初、原価を下げようとして魚の質を落としたところ、リピート率が激減しました。結局、高品質な食材に戻すまでに半年も要し、その間に失った顧客を取り戻すのに倍の時間がかかった」と振り返ります。
食材の質は顧客体験の核心部分。一度失った信頼を取り戻すコストは、節約できた金額をはるかに上回ります。
広告・マーケティング予算のゼロカット
資金繰りが厳しくなると真っ先に削られがちなのが広告予算です。しかし、認知度が低い開業初期にこそ、効果的なマーケティングが不可欠です。
「AFURI」を全国展開した佐藤氏は「開業半年で広告費を全カットしたら、来客数が40%も減少した。その後の回復に予算の3倍以上かけることになった」と警告します。
重要なのは予算削減ではなく、費用対効果の高いマーケティング手法への転換です。無料のSNS活用やローカルな口コミ戦略など、小予算で効果を最大化する方法を模索しましょう。
スタッフトレーニングへの投資削減
人件費削減の名目で、スタッフ教育を疎かにする経営者は多いものです。しかし、接客スキルや調理技術が不十分なスタッフによる低品質なサービスは、顧客満足度を直撃します。
ミシュラン星付きレストラン「虎白」の森氏は「開業時のスタッフ研修を短縮して早く開店したことが最大の失敗。結果的に再教育のために休業せざるを得なくなり、機会損失は研修費用の10倍以上だった」と証言します。
適切なトレーニングを受けたスタッフは単なるコストではなく、店の価値を高める資産です。
メンテナンスの先送り
厨房機器や店舗設備のメンテナンスを後回しにする判断は、短期的には資金流出を抑えられますが、長期的には致命的な問題を引き起こします。
「今、使えているから大丈夫」という考えが、営業中の機器故障やそれに伴う休業という形で跳ね返ってきた例は枚挙にいとまがありません。
福岡の人気ラーメン店「一蘭」創業者の吉冨氏は「予防的メンテナンスを怠ることで一日の営業がストップした場合、その損失は予防メンテナンスコストの何倍にもなる」と語ります。
成長のための投資を全て凍結する
赤字を恐れるあまり、将来の成長につながる投資をすべて凍結するのは大きな間違いです。戦略的に重要な投資は、たとえ初期費用がかかっても長期的なコスト削減や売上増加に貢献します。
例えば、注文システムのデジタル化は初期費用がかかりますが、オーダーミスの減少、回転率の向上、スタッフ効率化など多面的な効果をもたらします。
全国に40店舗を展開する「叙々苑」の会長は「開業初年度に全ての投資を止めたのではなく、投資の優先順位を明確にし、効果の見込める施策に集中投資したことが、その後の成長の礎になった」と強調しています。
開業初年度は経営の土台を固める重要な時期です。近視眼的なコスト削減よりも、価値を維持・向上させながら効率化を図る「スマートな節約」が、持続可能な飲食店経営の鍵となるでしょう。
4. **立地選びで8割が決まる!飲食店のロケーション選定で見落としがちな重要ポイント**
タイトル: 初めての飲食店開業で絶対やってはいけない5つのこと
見出し: 4. 立地選びで8割が決まる!飲食店のロケーション選定で見落としがちな重要ポイント
飲食店の成功は立地で8割決まると言われるほど、ロケーション選びは開業において最も重要な要素の一つです。「とりあえず人通りの多い場所」と単純に考えてしまうと、後々大きな失敗につながりかねません。ここでは多くの新規オーナーが見落としがちな立地選定の重要ポイントをご紹介します。
まず最も見落とされがちなのが「ターゲット層と立地の整合性」です。例えば、高級フレンチレストランを若者の多いアミューズメント街に出店しても集客は難しいでしょう。逆に、リーズナブルな居酒屋をオフィス街の高級ビル内に出すのも不適切です。自分のコンセプトとターゲットに合った街区を選ぶことが重要です。
次に注目すべきは「周辺の競合店舗の状況」です。類似店が多すぎる場所は避けるべきと思われがちですが、実はある程度の競合店の存在はその地域に特定の食文化や需要が確立されていることを示しています。「ラーメン激戦区」「イタリアン通り」など、同業種が集まることで集客力が高まるケースもあるのです。
また「歩行者の流れと視認性」も重要です。単に通行量が多いだけでなく、店舗が視界に入る角度や歩行のテンポなども集客に影響します。特に駅からの帰宅ルート上にあるか、それとも寄り道が必要な立地かで大きく集客力が変わります。サイゼリヤやマクドナルドなどの成功チェーン店の立地を観察すると、この「人の流れ」を巧みに捉えていることがわかります。
見落とされがちなのが「物件の前歴」です。何度も飲食店が入れ替わっている物件には何らかの構造的問題がある可能性があります。逆に長く営業していた飲食店の跡地は設備や客層の基盤があるため有利なケースもあります。例えば、東京・銀座の「鮨青木」は以前別の有名寿司店があった場所で開業し、既存客層をうまく引き継いだ成功例として知られています。
最後に「将来的な街の変化」も考慮すべきです。再開発計画や新駅建設、大型施設のオープンなど、将来の変化を先読みすることで、今は人通りが少なくても数年後に価値が上がる立地を見極められます。横浜の「みなとみらい」エリアや渋谷の「宮下公園」周辺の飲食店は再開発の波に乗って成功した例と言えるでしょう。
立地選びは一度決めると簡単には変えられません。物件の家賃や条件だけでなく、これらの多角的な視点から検討することが、飲食店開業成功への重要なステップとなります。
5. **メニュー開発の致命的ミス - 利益率と顧客満足度を両立させる飲食店経営の秘訣**
5. メニュー開発の致命的ミス - 利益率と顧客満足度を両立させる飲食店経営の秘訣
飲食店開業において、メニュー開発は店舗の命運を左右する重要な要素です。しかし、多くの新規オーナーがこの段階で致命的なミスを犯しています。利益率だけを追求して顧客満足度が低いメニューを提供すれば、リピーターの獲得は難しくなります。逆に、原価率が高すぎるメニューばかりでは、店舗の経営が立ち行かなくなるリスクがあります。
最も避けるべき失敗は「中途半端なメニュー構成」です。コンセプトが曖昧で、何でも提供する八方美人的なメニューは、専門性の欠如から顧客の心を掴めません。日本料理店なのにパスタもカレーもある…という状況は、どのジャンルも中途半端な印象を与えてしまいます。サイゼリヤやロイヤルホストなどの成功チェーン店でさえ、明確なコンセプトと価格帯を持っています。
また、原価計算の甘さも大きな問題です。食材コストだけでなく、調理時間や手間も含めた総合的な原価を考慮せず、見た目の食材費だけで判断してしまうケースが少なくありません。例えば、一見原価が安く見える手の込んだ料理も、調理に時間がかかりすぎると人件費が膨らみ、結果的に利益を圧迫します。
さらに、顧客視点の欠如も致命的です。「自分が美味しいと思うから」という理由だけでメニュー開発を進めると、ターゲット顧客のニーズとのミスマッチが生じます。実際に繁盛している飲食店は、常に顧客の声に耳を傾け、データに基づいたメニュー改善を継続しています。
メニュー開発で成功するためには、まず明確なコンセプトを定め、ターゲット顧客を絞り込むことが不可欠です。次に、原価率30〜35%を目安に、高利益率商品と目玉商品をバランスよく配置します。定期的な顧客アンケートやABCランキング分析を通じて、人気メニューと不人気メニューを把握し、常に改良を重ねていくことが持続可能な飲食店経営の鍵となります。
業界の成功事例を見ると、オープン前に徹底的な試食会を実施し、第三者の意見を取り入れたメニュー開発を行っている店舗が多いことがわかります。また、季節メニューの導入で定期的な来店動機を創出するなど、顧客満足と収益性を両立させる工夫が重要です。
投稿者プロフィール

- 飲食マーケティングライター
- 飲食店繁盛会のアシスタント。様々な業務を行い、なんでもできる。いろんなところで活躍している。
最新の投稿
 飲食店コラム2025年6月2日客単価を無理なく上げる!飲食店の売上アップ7つの秘訣
飲食店コラム2025年6月2日客単価を無理なく上げる!飲食店の売上アップ7つの秘訣 飲食店のDX2025年5月30日ネット広告費を半分に削減しながら成約率2倍にした戦略
飲食店のDX2025年5月30日ネット広告費を半分に削減しながら成約率2倍にした戦略 飲食店のDX2025年5月28日ワードプレス初心者が3ヶ月で月間10万PV達成した方法
飲食店のDX2025年5月28日ワードプレス初心者が3ヶ月で月間10万PV達成した方法 飲食店コラム2025年5月26日お金をかけずに効果絶大!飲食店ゲリラマーケティング入門
飲食店コラム2025年5月26日お金をかけずに効果絶大!飲食店ゲリラマーケティング入門

私たちがあなたのお店にお役に立てることは
ございませんでしょうか?
もし、何かありそうでしたら、
お気軽にお話を聞かせてください。
無料相談の詳細・お申し込みはこちら
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問など
お気軽にお問い合わせください